言葉で何を届けたいのか — CLIL研究を通じて探る理論と実践
英語担当:上野 育子 准教授(専任教員)
2025/11/04
研究紹介
OVERVIEW
立教大学外国語教育研究センター上野育子准教授(英語担当)にご自身の研究内容や今後の抱負等についてお聞きしました。
先生の研究テーマや、現在取り組まれている研究についてお聞かせください。
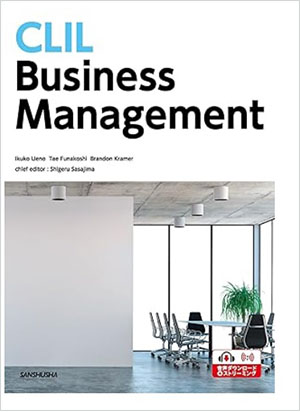
初めてのCLIL教科書出版『経営学入門』
私の研究テーマは、CLIL(内容言語統合型学習)を基盤とした大学英語教育です。博士論文では授業内言語使用に関する教師と学習者のビリーフを扱い、その延長でCLILに関心を持ちました。現在はCLILがEMI(英語による授業)への効果的な架け橋となり得るかを探究し、学生の声や授業実践を分析しています。また経営学を対象にしたCLIL教材を出版し、他分野でも教材開発を進めています。さらに、2024年度のCLILカリキュラム導入に加え、2028年度の大規模なカリキュラム改編にも携わり、研究成果を教育改革に直接つなげることを目指しています。
ご自身の研究に興味を持ったきっかけについてお聞かせください。

CLILの第一人者 Do Coyle氏と学会にて
英語を教える仕事は長年取り組んできたライフワークですが、ある時「自分自身が学び続けなければ教える内容が枯渇してしまうのではないか」と感じ、大学院に戻る決心をしました。当初は修士課程だけのつもりでしたが、在学中に教職課程も取得し、さらに学びを深めたいとの思いから博士課程へと進みました。ちょうどその頃、中学・高校でも英語による授業が文科省から奨励され始め、授業内での母語使用と目標言語使用のあり方に強い関心を持つようになりました。その探究が博士論文のテーマとなり、現在のCLIL研究へとつながっています。
ご自身の研究の面白さ・醍醐味はどのような点にあるとお考えでしょうか。
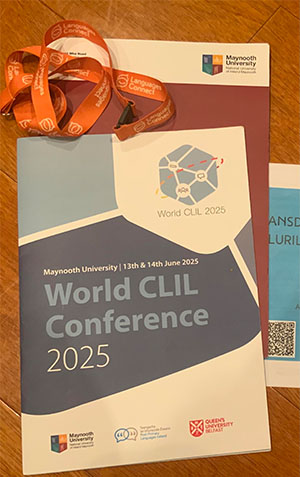
World CLIL 2025学会資料
私の研究の面白さは、理論と実践が密接に結びついている点にあります。特にCLIL研究では、研究者であり実践者=practitionerとして、教員自身が「教える」ことを通して学生と共に学びを深めていけることに大きな魅力を感じます。授業実践や担当する学生からのフィードバックを通じて、ファシリテーションや教材設計の工夫が学習意欲や理解度に直結することを実感でき、学生の成長がそのまま研究成果として可視化されます。授業での小さな工夫が学生の自信や主体性を引き出し、それがデータとして裏づけられる瞬間に、教育と研究が一体となる醍醐味を味わうことができます。
学生時代(大学や大学院、海外留学など)の経験や学んだことについてお聞かせください。

イギリスの風景
大学では文学部英文科に所属し、イギリス演劇を学びました。当時は自分が大学で教壇に立つ未来など想像もしていませんでしたが、学生時代はとても楽しく、人生の宝物のような時間でした。その頃の友人とは今でも折に触れて集まり、絆を大切にしています。大学という場所は学問の場であると同時に、人生をどう生きるかを模索する準備期間だと感じます。学びや人との出会いの一つひとつが後の人生を支える財産となりました。また、イギリス・オックスフォードでの一年間の留学は、私の世界を大きく広げてくれた経験です。言語のみならず異文化や生活習慣を直接体感することの意義を、若い時期に強く実感することができました。
現在の大学でのお仕事について。内容や、楽しいところ、大変なところを教えてください。

World CLIL 2025学会後、ロンドンにて
大学での仕事は授業・研究・運営と多岐にわたりますが、やはり一番の喜びは学生と共に歩む授業の時間です。14回の授業は、初回の出会いから始まり、少しずつ名前と顔を覚え、タスクを重ねるごとに学生の考え方や知識とつながっていきます。最終日には、学生が何か一つでもこのコースから学びを持ち帰ってくれることを願いながら送り出します。その過程で交わす対話や、時に届く嬉しい言葉やメールこそが、教員としての自分にとっての真の喜びです。もちろんカリキュラム改革や運営の責務は大変ですが、学生との出会いと成長の瞬間が、日々の励みになっています。
ご自身の今後の抱負や夢、研究計画についてお聞かせください。
今後は、日本の大学教育の実情に合わせて、複言語・複文化の視点をより強く取り入れ、教育実践と研究の双方を深めていきたいと考えています。そのためにも、2024年度から導入されたCLILコースで収集したデータを分析し、論文として発表しながら成果を丁寧に検証することが、まず取り組むべき課題です。その上で、2028年度のカリキュラム改編では、CLILにとどまらず多様な授業を展開し、学生の継続的な言語学習を支える基盤を築くことを目指しています。また、CLIL教材の開発や教員研修の枠組みづくりにも力を注ぎ、研究成果を教育現場へ還元することで、より多くの学生が興味をもって英語を学ぶことができる環境を整えていくことが、今の私の大きな目標です。※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。
